草刈機を購入する際、多くの方が直面する悩みが「電動式」と「エンジン式」のどちらを選ぶべきかという点です。それぞれの草刈機には、価格やパワー、操作性、メンテナンスのしやすさ、作業音、燃料・電源の違いといった多くの要素において違いがあります。さらに、草刈機を使う環境や頻度、作業者の年齢や体力なども、選ぶべきモデルに大きく関わってきます。
 モアっち
モアっち草刈機を初めて買うときって種類が多すぎて、
どれを選んでいいかわからないよね💦
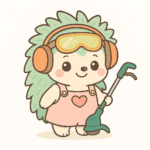 モアみん
モアみん以前はエンジン式が当たり前だったんだけど、最近はバッテリー式も主流になりつつあるのよね!
たとえば、自宅の狭い庭で月に1〜2回だけ草を刈る場合と、広大な農地や空き地を毎週のように整備する場合では、必要なパワーや稼働時間、安全対策もまったく異なります。また、住宅街のように周囲に音が響きやすい環境では静音性も重要な選定基準になります。小さなお子さんやペットがいる家庭では、音量の少なさや安全機能の充実度が購入の決め手になることもあります。
さらに、現在は各メーカーから家庭用・業務用を問わずさまざまなモデルが販売されており、バッテリー技術の進化によって電動モデルも一昔前とは比べ物にならないほど高性能になっています。軽量化やパワー強化、さらにはバッテリーの大容量化により、エンジン式に迫る性能を発揮する機種も登場しています。一方、エンジン式には高負荷作業に耐えるタフな構造と、長時間連続使用が可能という優れた特性があり、プロの現場では今なお主流といえる存在です。
また、作業に必要な付属品や安全装備、季節による使い分け方といった実践的な情報も交えながら、実際に草刈機を使用する現場で役立つ知識をお届けします。これから初めて草刈機を購入する方、現在の草刈機からの買い替えを検討している方、どちらにとっても納得できる一台を見つけるための強力なガイドとなることを目指しています。
草刈機の基本構造と種類
電動草刈り機の特徴と種類

電動草刈機は、モーターを動力とするタイプで、軽量・静音で扱いやすいのが特徴です。操作がシンプルなこともあり、機械に不慣れな方でも取り入れやすいのが魅力です。以下の2タイプがあります:
- コード式(AC電源):コンセントから電源を供給し続けるため、長時間の作業が可能です。安定したパワーを維持でき、家庭の庭などでの使用に向いています。ただし、電源のある場所に限られるうえ、コードの取り回しに気を使う必要があり、狭い場所や障害物が多い場所では不便になることもあります。延長コードを使うことで多少の可動域は広がりますが、コードが絡まったり、切断のリスクがあるため注意が必要です。可搬性の高さが最大の魅力です。電源の確保が不要なため、庭から畑、敷地の隅々まで移動しながら作業ができ、操作の自由度が高いのが特長です。バッテリー切れには注意が必要ですが、予備バッテリーを持っていれば作業を中断せずに継続可能です。また、騒音が少ないため住宅街や朝夕の作業にも適しています。
- コードレス(バッテリー式):リチウムイオンバッテリーを使用して動作します。可搬性に優れ、コードがないため自由に移動しながら作業ができるのが大きなメリットです。小型の18Vをはじめ、最近では36Vや40Vの高電圧モデルが普及しており、従来よりもパワーが大幅に向上しています。家庭用からプロ仕様までラインナップが豊富で、替えバッテリーを持つことで連続作業も可能となります。環境への配慮として、CO₂を排出しない点も評価されています。可搬性の高さが最大の魅力です。電源の確保が不要なため、庭から畑、敷地の隅々まで移動しながら作業ができ、操作の自由度が高いのが特長です。バッテリー切れには注意が必要ですが、予備バッテリーを持っていれば作業を中断せずに継続可能です。また、騒音が少ないため住宅街や朝夕の作業にも適しています。
エンジン式草刈機の特徴と種類

エンジン草刈機は、ガソリンエンジンを搭載し、出力が強く、長時間の作業にも耐えるタフな構造が特徴です。プロの現場や農業、造園業などでも多く採用されており、草丈の高い雑草やツル性植物、密集地での使用に最適です。以下の2タイプが代表的です:
- 2ストロークエンジン:軽量でコンパクトな設計が多く、取り回しの良さが特徴です。混合燃料(ガソリンとオイルを所定の比率で混ぜる)を使用しなければならない点が少し手間ではありますが、スタートも比較的容易で初心者でも扱いやすいタイプです。
- 4ストロークエンジン:ガソリンとエンジンオイルを別々に使用するタイプで、排気音が静かで振動も少なく、燃費に優れているのが特徴です。長時間作業でも疲労を感じにくく、環境にも優しいモデルといえます。ただし、2ストに比べると若干重くなる傾向があり、保守点検もやや複雑です。※混合燃料タイプもあるため使用には注意が必要
また、肩掛け式や背負い式など、作業スタイルに応じて選べるバリエーションも多く、広範囲での作業にも適応しやすいのが強みです。
電動草刈り機のメリット・デメリット

メンテナンス性
電動式草刈機は、ガソリンエンジンと異なりオイル交換や燃料補充といった定期的なメンテナンスが必要ありません。これにより、初心者や機械に不慣れな方でも安心して扱える点が大きな利点です。さらに、始動もスイッチを押すだけで済むため、エンジンのようにリコイルスターターを引く煩わしさがなく、すぐに作業を開始できます。刃の清掃やボディの拭き取りといった日常的なケアだけで運用可能であり、維持コストも比較的抑えられます。また、定期的な点検や分解整備が不要なため、長期的に見てもメンテナンス負荷が圧倒的に軽いのが特徴です。
騒音・使用場所の自由度
電動草刈機はモーター駆動のため、エンジン式に比べて稼働音が非常に小さく、早朝や夕方の作業でも周囲に配慮しながら使用できます。特に住宅密集地や学校、病院の近くなど、騒音が問題になりやすい環境での作業に適しています。また、排気ガスも発生しないため、閉鎖的な庭やハウス内での使用にも向いています。静音性に優れたことは、使用者のストレス軽減にもつながり、作業に集中できるというメリットもあります。さらに、作業後の臭いも少ないため、使用後の片付けも快適です。
バッテリー寿命やパワーの限界
一方で、電動草刈機(特にバッテリー式)には、使用可能時間の制限という弱点があります。多くのモデルは1回の充電で30〜60分程度の稼働が限度となっており、広範囲の作業には複数のバッテリーが必要になる場合があります。また、バッテリーの寿命は充放電の回数に左右され、使用頻度が高いと数年で交換が必要になるケースもあります。さらに、高密度の雑草や太い茎、傾斜のある地形ではパワー不足を感じることがあり、こうした条件下ではエンジン式のほうが優位になることも否めません。ただし、最新モデルでは大容量バッテリーや高トルク設計が進化しており、この弱点は徐々に克服されつつあります。
エンジン式草刈機のメリット・デメリット

高出力で広範囲作業向き
エンジン式草刈機の最大の強みは、何といってもその高出力性能にあります。燃料を補充するだけで長時間の連続作業が可能で、電源に頼らず広範囲の草刈りを行えるため、農業や造園業、公共施設の維持管理など業務用の現場では今なお主力機種とされています。雑草が密集していたり、丈が高く根が深い植物が多い場合でも、エンジン式であれば刃が止まることなくスムーズに作業を続けることが可能です。また、傾斜地や山間部など電動モデルではパワー不足を感じやすいシーンでも安定したパフォーマンスを発揮します。長時間にわたる作業においても燃料補給をすれば即座に再開でき、作業効率を維持できる点はプロユースには欠かせない特長です。
重量・騒音・振動といった課題
高出力と引き換えに、エンジン式にはいくつかの物理的なデメリットもあります。まず重量に関しては、モーターと比べて構造が複雑かつ頑丈な分、必然的に本体が重くなりやすく、長時間の使用では腕や肩、腰への負担が大きくなります。さらに、エンジンの回転による騒音は想像以上に大きく、特に住宅街や静音を求められるエリアでは作業時間帯に配慮が必要となる場合があります。振動も強いため、長時間作業すると手のしびれや疲労感が残るケースも多く、防振手袋などの装備が必要になることもあります。これらの要素は高齢者や体力に不安のある方にとって大きな障壁となることがあるため、使用前に試運転や事前確認をしておくことをおすすめします。
混合油やメンテナンスの手間
エンジン式草刈機、特に2ストロークモデルでは、ガソリンとエンジンオイルを一定の比率で混ぜた混合燃料を使用する必要があります。適切な混合比(例:50:1、25:1など)を守らないとエンジン内部にカーボンが溜まりやすくなり、パフォーマンス低下や故障の原因になるため、燃料の準備には多少の知識と手間がかかります。また、始動時にはチョークの調整やスターターを引く力も求められ、電動に比べて準備工程がやや複雑です。定期的なキャブレターの掃除、エアフィルターの交換、スパークプラグの点検といったメンテナンス作業も欠かせません。エンジンを長持ちさせるためには、日頃からの管理が必須となるため、使用頻度が高い場合ほどメンテナンスの時間と手間が発生します。しかし、その反面でしっかり手入れすれば10年以上使える耐久性を誇るのもまた事実であり、長期運用を前提とした堅牢な選択肢でもあります。
使用シーン別・最適な選び方
一般家庭の庭・狭いスペース
一般家庭での草刈り作業は、主に庭や駐車スペースの周辺、あるいは花壇やフェンス際といった狭いエリアが中心となります。こうした場所では、コンパクトで取り回しがよく、騒音や振動が少ない草刈機が理想です。そのため、**電動草刈り機(特にバッテリー式)**が非常におすすめです。騒音が控えめで早朝や夕方の作業にも適しており、住宅密集地でも近隣に配慮しながら使用できます。
加えて、電動モデルはスイッチを押すだけで始動できるため、エンジン式に比べて操作がシンプルで使いやすく、力のない方でも安心して扱えます。最近では家庭向けに特化した軽量・コンパクトモデルも登場しており、バッテリー1本で30〜40分程度の連続作業が可能な製品が多く、草丈がそこまで高くない家庭の庭には十分なスペックと言えるでしょう。
広い農地・河川敷・空き地など
広い面積の雑草を一度に処理したい場合や、定期的に伸びる雑草の管理が求められる現場では、エンジン式草刈機が最も適した選択肢となります。特に2ストロークエンジンを搭載したモデルは、出力が高く、長時間にわたる連続作業にも耐えられる設計となっているため、農業や造園業、管理作業に携わるプロにも広く採用されています。
広大な土地では電源の確保が難しく、コード式の電動草刈機では対応できませんし、バッテリー式でも途中で充電が必要になるケースが多いため、燃料の継ぎ足しで即作業を再開できるエンジン式は大きな利点です。特に背負い式モデルや肩掛け式モデルは、身体全体に荷重を分散できる構造になっており、長時間の作業時の疲労軽減にも役立ちます。
高齢者や女性にとっての扱いやすさ
年配の方や女性にとって草刈機の選定は、「軽さ」と「操作性」が重要なポイントとなります。このようなユーザーには、軽量タイプの電動草刈機がおすすめです。バッテリー式モデルの中には、本体重量が2kg台という非常に軽い製品もあり、片手でも扱える機種が存在します。
また、振動が少なく、操作スイッチも直感的でわかりやすいため、初めての使用でも安心感があります。安全面でも、誤作動防止スイッチやソフトスタート機能が搭載されたモデルが多く、作業中の不安を最小限に抑える設計が施されています。さらに、草刈りを頻繁に行わないユーザーにとっても、メンテナンスの手軽さは大きな魅力です。
必要であれば、軽量タイプに加えてハンドルの高さや角度が調整可能なモデルを選ぶことで、体格に合わせた作業姿勢が取れ、腰や肩への負担を軽減することができます。
初心者におすすめのモデルと選び方ポイント

ハンドル形状の使い分けについて
- U字ハンドル(両手ハンドル):両手でしっかり握ることができるため、左右への振り幅が安定し、広い範囲を効率よく刈ることが可能です。長時間作業や広い面積の草刈りに向いており、農地や空き地の管理作業に最適です。
- ループハンドル:片手で本体を支えつつ、もう一方の手でループ状のハンドルを握って操作します。狭い場所や障害物の多い庭先など、小回りが必要な場所に適しています。柔軟な動きが可能なので、家庭用として人気の高いスタイルです。
- ツーグリップ(棒状グリップ):軽量モデルに多く見られる形状で、手軽に取り回しできる反面、長時間の使用には向いていません。短時間・軽作業や草丈の低い場所など、限定的な用途に適しています。
ハンドルの形状は、作業スタイルや使用者の体格、操作性に直結するため、必ず事前に確認して選ぶことが大切です。
有名メーカー紹介(マキタ・HiKOKI・ゼノア等)
草刈機選びで迷ったときに、まず注目すべきは信頼できるメーカーの存在です。初めて草刈機を扱う方にとって、操作のしやすさや安全性、製品の品質が確保されているメーカーを選ぶことは安心感にも直結します。以下の3社は、日本国内で高いシェアを誇る代表的なメーカーです。
- マキタ:電動工具のパイオニアとして知られるマキタは、草刈機分野でも多数のモデルを展開。特にバッテリーの互換性が高く、すでにマキタ製品を使っている方には非常にコストパフォーマンスが良い選択肢となります。住宅地向けの静音モデルや軽量機種も豊富です。
- HiKOKI(旧:日立工機):バッテリー技術と静音性に定評があり、女性や高齢者でも扱いやすい軽量設計のモデルが揃っています。安全性や快適性を重視する方におすすめで、デザイン性にも優れた製品が多いのも特徴です。
- ゼノア:本格的なエンジン式草刈機で業界トップクラスの実績を持つゼノアは、農業従事者や造園業者からの信頼が厚いブランドです。高出力と耐久性を両立しており、プロユースを前提とした製品設計が光ります。
必須の安全機能とオプション
草刈機を安全に使いこなすには、製品そのものに備わっている安全機能や補助的なオプションにも注目する必要があります。特に初心者の場合、誤作動や事故を未然に防ぐための装備は必須です。
- 二重スイッチ(誤作動防止):誤ってスイッチを押したときでも刃が作動しない安全機構。
- キックバック防止設計:硬いものに当たっても跳ね返りを抑制し、使用者の安全を守ります。
- 飛散防止ガード:刃の周囲をカバーすることで、石や草の飛び散りを防ぎ、周囲への配慮にも繋がります。
- 肩掛けベルト・防振ハンドル:作業中の体の負担を軽減し、長時間の作業にも対応。特に防振機能付きのハンドルは、手や腕の疲労を大幅に和らげてくれます。
さらに、オプション品として安全メガネやイヤーマフ、滑り止め付きグローブなども併用すると安心です。
アフターサービス・保証内容もチェック
草刈機は長期間使う製品だからこそ、購入後のアフターサポート体制も重要です。信頼できるメーカーは、保証期間が長いだけでなく、修理対応の迅速さや部品供給の安定性にも力を入れています。
特に注意したいのは、交換部品の取り寄せやすさ。ローカルな機種や海外製のノーブランド品だと、数年後に部品が手に入らず修理不能になるケースもあります。国内メーカーや正規代理店を通じた製品であれば、全国規模の修理ネットワークが整備されており、万が一のトラブル時も安心です。
また、製品登録によって保証期間が延長されたり、定期点検の案内が届いたりするなどの付加価値がある場合もあるため、購入時に必ずチェックしておきましょう。
権威ある資料から見る草刈機の選び方
草刈機に関する正しい知識を持つには、実際に利用しているユーザーの声やネット上のレビューも参考にはなりますが、やはり最も信頼性が高いのは公的機関やメーカーが発行している公式な資料です。こうした情報源は、製品の仕様や使用方法、安全基準に関する詳細な情報が網羅されており、初心者から上級者まで安心して参照できます。
参考資料:
これらの資料では、草刈機の基本的な構造から始まり、エンジンやモーターの仕組み、メンテナンスの方法、安全に使用するためのチェックポイント、保管時の注意点に至るまで、非常に細かく解説されています。特に「農林水産省のマニュアル」は、農家や業務従事者だけでなく、家庭菜園やガーデニングを趣味とする個人にも活用できる内容となっており、イラスト付きでわかりやすく構成されています。
また、JA全農が提供している技術資料や定期的に開催している講習会では、現場での草刈機事故の実例とその対策、最新の製品動向なども紹介されています。こうした情報は製品選びだけでなく、実際の使用時の安全対策にも直結します。
さらに、各メーカーの公式カタログやウェブサイトでは、モデルごとの特性比較や推奨使用環境、安全機能の有無、保証内容などを詳細に確認することができます。とくにマキタやゼノア、スチールといった大手ブランドでは、PDFでの仕様書ダウンロードや動画解説も充実しており、製品を選ぶ際の判断材料として非常に有用です。
初心者ほど、こうした信頼できる資料を活用することで、誤った使い方や過大な期待による失敗を避けることができ、安全かつ長持ちする草刈機の運用に繋がります。


コメント